前回、マイナンバーカードの話をちょっと書いたのだが、利用法はこれからもう少し広がってきそうな感じである。
前回の記事では、給付の一部がマイナンバーカードを作る事で増える可能性があるよ、だから作ろうぜ、という話であった。
以降、ちょっとマイナンバーカードでできる事を色々調べているのだが、こんなニュースがあったので紹介しておきたい。
通院中の人はマイナンバーカードの健康保険証利用がおすすめ。令和3年分から医療費の確定申告が簡単に。
更新日: 2021.11.15
2021年10月20日より、マイナンバーカードの健康保険証利用が本格的にスタートしました。しかし、この制度について詳しく知らない人、具体的にイメージできない人はまだまだ多いでしょう。
「ファイナンシャルフィールド」より
ここではマイナンバーカードを保険証利用するメリットや申し込み方法、利用できる医療機関の確認方法を解説します。参考にして、マイナンバーカードの保険証利用をぜひ検討してください。
便利に使える?!
そもそも確定申告って?
医療費の確定申告って何?
そもそも「医療費の確定申告」って何?という話を少し。
先ずは確定申告について。
所得税の確定申告とは、1年間の所得(売上から経費を差し引いた儲け)をとりまとめて所得にかかる税金を計算し、国(税務署)に納めるべき税額を報告する手続きのこと。
「弥生のサイト」より
分かったような分からないような説明なのだけれど、例えばサラリーマンであれば所得に対して所得税が差し引かれた状態で給与を貰うので、「関係ない」という風に思う人が多いのではないか。これは、パートをやっている奥様も似たような感じの話になる。
しかし、自営業の方は所得に対してかかる所得税は、所得を得た段階ではかからないので、年度末にその税金額の確定をするという作業が必要になってくる。
僕はサラリーマンなので「関係ないよ」という話になるかというと、しかしそうではないんだよね。例えば、病院にかかって医療費を支払った場合には、税金に対する控除が発生するので、確定申告をすることで、還付を受ける(お金が戻ってくる)ことができる。主たる給与収入が2000万円を超える方は必須になるし、年末調整が出来なかった場合にも必須になるらしいけれど。
まあ、詳しい事は国税局のサイトを読んで頂ければ分かると思う。
医療費に関してはこちら。
この他、個人で不動産を所有していて利益を得ていたり、株取引などで利益を得ていたりする場合には、そこに所得が発生するために所得税がかかる。副業をやっている人は基本的に確定申告が必要であるという事を理解しておくひつようがある。
とまあ、そんな訳で、納めた税金が多ければ還付を受ける事ができるし、少なければ支払わなければならないというのが、確定申告なのである。
確定申告をしないとどうなるの?
国民の義務として、納税の義務がある。
したがって、自分が支払うべき税金の把握も国民の義務という事になって、確定申告は「必要であれば行わなければならない」ことである。
そんな訳で、確定申告をしない人にはペナルティが発生する。一般的には以下のようなペナルティがある。
- 納める税金に最高税率20%の無申告加算税がかかる
- 納める税金に最高税率14.6%の延滞税がかかる
- 青色申告特別控除の枠が、最大65万円から最大10万円に減額される
- 2年連続で提出が遅れると青色申告の承認が取り消しになる
自営業をやっておられる方は「青色申告」が必須業務となる。しかし、サラリーマンでもその対象になるんだよね。ただ、多くの人は「還付を受け取っていない」だけなので問題になりにくい。
学校では教えてくれない話なのだけれど、先生がそもそもそうした知識がない方ばかりなので、仕方が無いのかも知れない。
あ、そういえば来年から高校の授業に「公共」という科目が増えるというニュースがあったね。その辺りで教えてくれないかしら。
来春から高校必修「公共」ってどんな内容? SDGs、模擬選挙、領土…「主体的、対話的」学び促す検定教科書
2021年3月31日 06時00分
来年4月から全国の高校で使われる「公共」の教科書は、国連のSDGs(持続可能な開発目標)など社会的に注目される問題を通じて自分の考えをまとめ、授業で話し合いを促す内容が、現行の「現代社会」と比べて目立つ。教育の専門家は「現場の先生が高校生の社会への疑問を受け止め、さまざまな視点を示してほしい」と願う。
「東京新聞」より
あまり期待出来ないかも知れない……。
確定申告はどうやって行うの?
さて、確定申告のやり方に関しては、例えば以下のようなサイトを参考にして欲しい。

で、確定申告のやり方なのだけれど、基本的には税務署に出向いて行うということになっている。ただ、利便性を図るために、年末には市役所などに出張所が設けられているので、そちらで確定申告を行うことも出来る。
税務署から書類を取り寄せて、郵送で書類を送って確定申告を完了することも出来る模様。
最近は、e-Taxを使ってPCやスマホからも確定申告ができる様になっているので、利便性が上がっているのだけれど、所得の種類が給与所得、雑所得、一時所得の場合に限るとのこと。つまり医療費の確定申告には対応していないんだよね。
医療費の確定申告をマイナンバーカードを使って行うには
そもそも医療費控除って?
さて、説明が長くなったのだけれど、確定申告の話はザックリと説明をした。
では「医療費の確定申告」とは何なのか?という話になると思うのだけれど、コレも少し説明が必要だと思う。
一定の額の医療費を支払ったときは、確定申告を行うことで所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。
・あなたや生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費があるときは、次の算式によって計算した金額が医療費控除として所得金額から差し引かれます。
・1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費に限って控除の対象となります。未払となっている医療費は、実際に支払った年の控除対象となります。
・通常の医療費控除の適用を受けることを選択した方は、セルフメディケーション税制を受けることはできません。
「国税庁のサイト」より
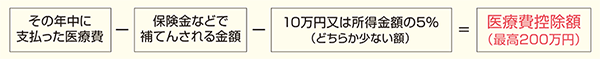
構図としてはこんな感じになっている。
医療機関にかかった方は、該当する可能性は高いだろう。
マイナポータルで「医療費通知情報」が管理できるようになる
しかし、一般人はどれがどのように該当するのかさっぱり分からない。基本的には以下のようなものが対象になるようだが。
<医療費控除の対象>
- 医師、歯科医師による診療や治療の対価
- 治療のためのあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価
- 助産師による分べんの介助の対価
- 医師等による一定の特定保健指導の対価
- 介護福祉士等による喀痰吸引等の対価
- 保健師や看護師、准看護師による療養上の世話の対価
- 治療や療養に必要な医薬品の購入の対価
- 病院、診療所又は助産所などへ収容されるための人的役務の提供の対価
分かり易いのは病院にかかった場合に、所定額を超えると対象になるという話。しかし、治療や医療に必要な医薬品の購入というのはちょっと分かりにくい。コレ実は、風邪薬を買って飲んだり、シップ薬を買って使った場合にも対象になるという意味だ。
案外、皆さん気にしていないんじゃないだろうか。
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額(1) 保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(2) 10万円
「国税庁のサイト」より
こうした計算式になっているので、その根拠となるレシートは残しておく必要がある。が、コレのサポートをしてくれるのがマイナンバーカード+マイナポータルの仕組みなんだとか。
医療機関、薬局がマイナンバーカードに対応している必要がある
ただ、コレ非常に大きな問題があって、マイナンバーカードを作ってある必要があるのがまず大前提で、ついでにマイナポータルのサイトを利用している必要があって、アプリをスマホにインストールしている必要がある。
更に、医療機関でマイナンバーカードを使える必要があるんだよね。これは今後増えて行くとは思うんだけど、今のところ僕の知っている医療機関のうち、大きな所は対応している感じだけど、小さなところは未だ導入が進んでいないようだ。
薬局もそう。
マイナンバーカードの健康保険証は、オレンジ色の「マイナ受付」のステッカーやポスターが掲出された医療機関・薬局で利用可能です。
「ファイナンシャルフィールド」より
お使いの医療機関でこのステッカーやポスターがあるかを確認しよう。
ということは、マイナンバーカードが利用できないところでは、この機能が使えないのはガッカリ仕様だし、市販の薬品を買った場合とかには対応出来ない模様。その辺りは他の方法に頼らざるを得ない模様。
うーん、そこは残念。
今後、医療機関が対応してくれれば利便性は向上してきそうだけれど、直ぐに医療費の確定申告に使えるぜ!という事では無さそうである。

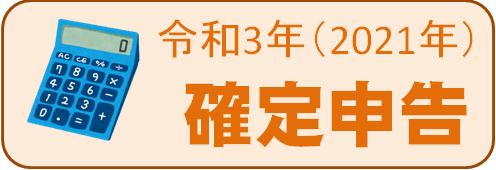



コメント